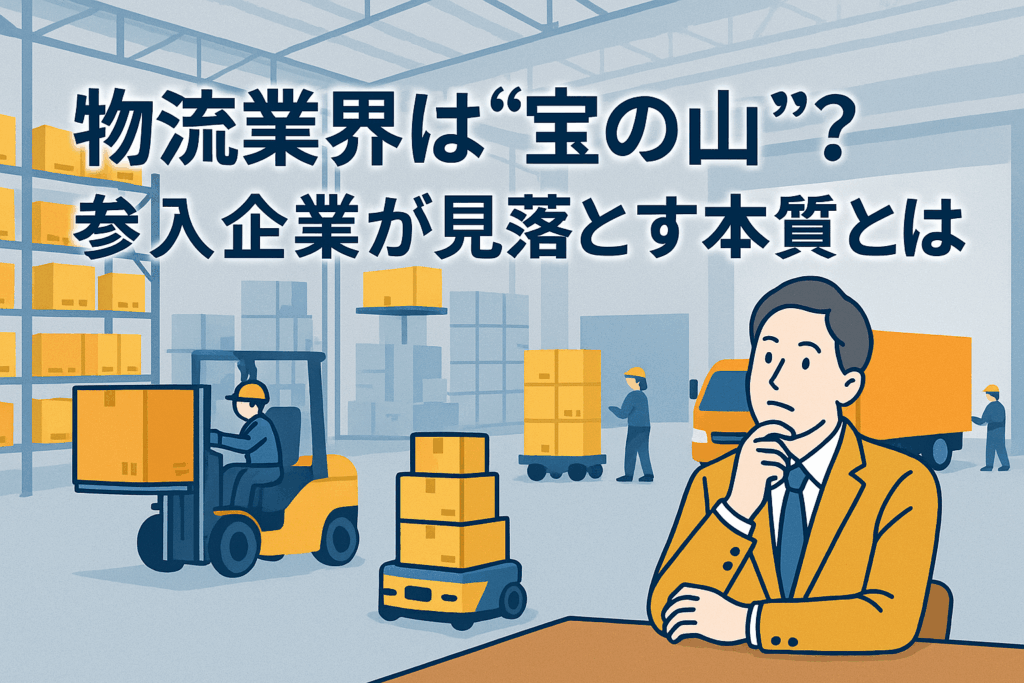今、物流業界が「ブルーオーシャン」として注目を集めています。
慢性的な人手不足、労働災害の増加、業務の属人化——こうした課題は山積していますが、裏を返せば“改善の余地が大きい”=“成長の余地がある”とも言えます。
だからこそ、IT企業や異業種からの参入が相次いでいます。
自動化・AI・ロボット・IoT・トラック予約システム……さまざまな最新技術が「物流改革の切り札」として投入され始めています。
しかし、実際の現場では——
「高額な設備を導入したけど、思ったほど使いこなせていない」
「人がルールを守らず、せっかくのシステムが空回りしている」
「そもそも、そのルール自体が“誰のため”にあるのか分からなくなってきた」
——そんな声が増えているのも事実です。
■ 現場のリアルを知らずして、成功はない
物流の現場は、机上の設計図通りには動きません。
日々、異なる人が入り、異なる荷物を扱い、状況が常に変化しています。
・AGVが走れない場所に人が荷物を置く
・検品済みのシールがどこにあるかわからず再検品
・ドライバーの導線がわからず、現場が混乱
・外注スタッフがルールを知らず、事故寸前に
どれも、「仕組みが悪い」わけではありません。
問題は、“人の行動”を前提にしていないシステム設計です。
つまり、現場のアナログな感覚を無視して、いきなりデジタル化しようとしても、現場に定着しないのです。
■ デジタルの前に必要なのは、アナログの思考
本当に大事なのは、「ルールがあること」ではなく、「ルールを守れる仕組みがあること」です。
その仕組みとは、“一目で分かる”“迷わず動ける”といった、アナログ的な工夫です。
私たちは、こう考えています。
いきなりシステムやロボットを入れる前に、人が迷わず動ける現場かどうかを、まず見直すべきだ。
実際、「ルールの“見える化”」や「サイン表示の改善」だけで、作業効率が上がった、ミスが減ったという現場は多くあります。
■ 現場力がなければ、DXは“空回り”する
これから物流業界に入ってくる新しい技術は、確かに魅力的です。
しかしそれらは、「現場力」があって初めて効果を発揮する“道具”にすぎません。
現場を知らずに仕組みだけを入れても、使いこなせずに終わる。
この事実に、すでに多くの企業が気づき始めています。
次回は、その事例をさらに掘り下げていきます。
▼次回予告
「AIもロボットも、現場を知らなければ役立たない」
――現場で起きている「自動化の落とし穴」とは?